アフィリエイト広告を利用しています。
 お台場
お台場こんにちは!お台場です。
今回は介護者の悩みとして、「嫌なヘルパーとどう向き合うか」を解説します。
介護を続けていると、普段助けてもらっているはずのヘルパーさんに『ん?』と違和感を覚えることがあります。
私の場合、スムーズに介護できるよう整理整頓を重視していますが、帰宅するとそれを乱しているヘルパーさんにストレスを感じることが多々あります。
この記事では、そんな私の体験をもとに、ヘルパーとの向き合い方を考えていきます。
- ヘルパーに違和感を抱き始めた方
- 相談しても改善が続かず、どうすればいいか悩んでいる方
- 感謝と不満の間で揺れ動いている方
- 「自分だけじゃない」と共感でき、心が軽くなります!
- 違和感への向き合い方や工夫が具体的に分かります!
- 感謝と葛藤を同時に持つ気持ちが肯定されます!
嫌なヘルパー=全てが嫌ではない


小さな違和感が積み重なって疲れる
私の介護生活はヘルパーさんなしには成り立ちません。日々支えて下さって頂き、本当に感謝しています。
ただその一方で、「ん?」とヘルパーさんに違和感を覚える瞬間も少なくありません。すべてが嫌というわけではありませんが、帰宅後の状況に引っかかりを覚える…。
こうした小さな違和感は、積み重なることで大きなストレスへとつながります。
相性や態度のズレはどの家庭でも起こりうる
ヘルパーさんも人間である以上、性格や価値観がそれぞれ違います。介護を受ける家庭側にも生活のリズムやこだわりがあり、その両方がぴったり合うことはむしろ珍しいものです。
たとえば、ある家庭では「テキパキ動くヘルパーがありがたい」と感じても、別の家庭では「落ち着いてゆっくり寄り添ってほしい」と望むかもしれません。同じ行動でも、受け取る側によって評価が変わるのです。
だからこそ「このヘルパーさんとは合わないのかも」と思うのは、介護者だけの問題でも、ヘルパーだけの問題でもありません。
人と人との相性や態度のズレは、どの家庭でも起こりうる自然なことだと受け止めることが、まず心を軽くする第一歩になります。
我が家の訪問介護
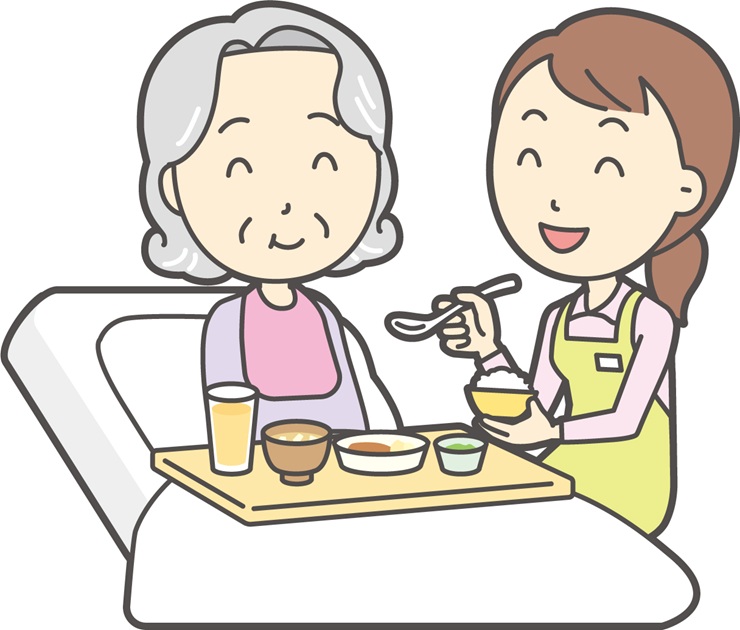
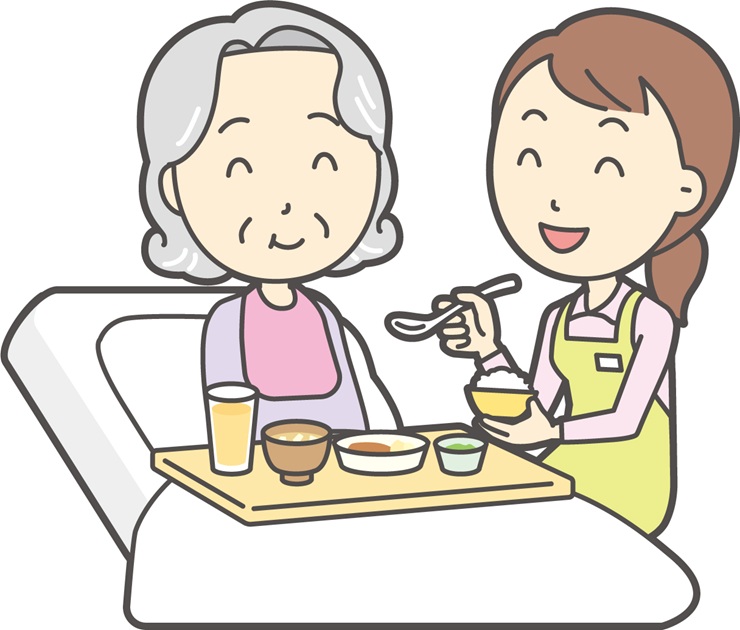
我が家の訪問介護はこんな感じです。現在はこの内容を、1週間当たり4人のヘルパーさんで対応して頂いています。
- ・訪問
-
ヘルパー1名×1時間×週5回(月~金の昼頃)
- ・時間
-
父母両方で1時間、父死去後は母のみで1時間
- ・休み
-
土日祝日+年末年始は私が対応する為、ヘルパーさん休み
<身体介護>
- ・食事
-
自身で食事可能な為、温め、開封等援助、片付け、服薬確認
- ・歯磨き
-
自身で歯磨き可能な為、歯磨きの準備、片付け、洗浄
- ・足浴
-
足浴用バケツにお湯を入れて対応、訪問入浴日はなし
- ・排せつ
-
ポータブルトイレの汚物除去・洗浄、消臭液添加、おむつ適宜交換
- ・粗相対応
-
汚れたパジャマやシーツの交換、汚物除去及び予洗い
<生活援助>
- ・軽微な掃除
-
足浴ない日に父母居室限定で掃除機かけ
- ・軽微な買い物
-
欲しい物(甘い物やサプリメント)を父が時々依頼(別契約)
<特記事項>
・女性ヘルパーのみの事業所を利用
足浴時、男性ヘルパーに足を触られるのを母が嫌がった為、途中で変更。性別の希望があれば、早めに親に聞いておくと良いでしょう。
私と母が感じた“違和感”の具体例


私は日頃、整理整頓を重視しています。工場勤務が長かったので「定位置に見やすく置く」ことへのこだわりが強め(笑)それがスムーズでストレスの少ない介護に繋がると思っています。
下記の具体例は、一見すると小さなことに思えるかもしれません。ですが整理整頓を大切にしている私にとっては、とても気になることでした。
私①|乱れた整理整頓
使った後、元通りに戻っていない状況に心がモヤモヤしてしまいます。
- 使った油性ペンを違うペン立てに入れられ、私が使う時無くて困る、イラっとする。
- お茶ティーバッグが入った袋の向きを裏返し。数種類あるので「緑茶」と書いてある方を表にし一目瞭然な状態にしているが、台無しに。
- 母のトレーは流し台に置かず、私のトレー置場に重ねて欲しい。帰宅後すぐ、重い買い物袋を流し台に置くので、そこにトレーがあると移動する手間が必要となり、ため息が出る。
- バーに掛けている風呂場用スリッパが、バーの隙間に突っ込まれ取りにくい状態に。
- 風呂場の操作パネルの蓋が開けっ放し、シャワー向きが変な方向に向けっぱなし。
私②|不衛生な違和感
- ポータブルトイレ用消臭液の空容器が、食卓テーブル上に置いてあり嫌な気分に。
- いつも吸水シート上に置いてある足浴用バケツが、なぜかストック用タオルの上に。明らかに不衛生。
私③|使ったコップそのまま
- 昼食時母へのお茶で、ヘルパー自身が使ったコップを洗わず洗い桶に放置する方がいます。洗ってくれるヘルパーがほとんどだが、なぜ洗わないのか疑問。たかがコップ1つ洗うだけだが、私の家事が確実に増えていて悲しい。
母①|不衛生な違和感
- コロナ禍前、風邪ではなく咳喘息だと言い、咳するヘルパー。普段言わない両親が私に咳が嫌だと訴えてきました。
母②|人柄への違和感
母がある日、こう言いました。
「あのヘルパーさん、人の悪口ばかり言うから苦手」
介護される側にとって、安心感は何よりも大切です。人の悪口が多いと、どうしても気持ちがネガティブになり落ち着かなくなります。
ここに記載した具体例はほんの一部です。こうした「ズレ」は日々起こっており、我々介護者や要介護者はその度に色々な感情に苛まれ、大きな疲労となってしまいます。
ヘルパーさんへの不満が出やすい原因


介護保険内でできる範囲が分かりづらい
下記の厚生労働省 通知文書を参考に、分かりづらさを整理します。
参考:同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(平成21年12月25日付け厚生労働省老健局振興課長通知)
訪問介護のQ&A



訪問介護ってどんなサービス?😫



ヘルパーが利用者宅を訪問し行うサービスで2種類あるよ~💡
①身体介護:食事や排泄、入浴などの介助
②生活援助:掃除や洗濯、食事の準備や調理など
②生活援助は「同居家族がいると出来ない」と機械的に判断されてきた実態が過去多くあり、この通知が発出された経緯があります。
②生活援助の線引きは「同居家族がいるかどうか」だけでなく「利用者の状態」、「利用する自治体の判断」などで可否が変わり、ケースバイケースとなっています。
利用者・家族にとっては「ヘルパーさんならこれくらいやってほしい」と思うことが多く、それが制度としてNGであったり、手続きや計画に入っていなかったりします。
この「できること・できないこと」が利用者・家族には分かりづらいのが実情。「なんでやってくれないの?」というギャップや不満につながりやすいのです。
誤解を防ぐためにできること
以下の理解があると、ヘルパーさんへの不満が減り、違和感もやわらぎます。
- サービス開始時に、ケアマネに「できる範囲」を具体的に確認する
- できないことが多い場合、「自費サービス」(保険外サービス)も検討する
- 「やってくれない=冷たい人」と短絡的に受け止めない
- サービス開始時は足りないことばかりに目が行くが、体制は少しずつ整うので焦らない
事務所へ相談したけど…改善は一時的
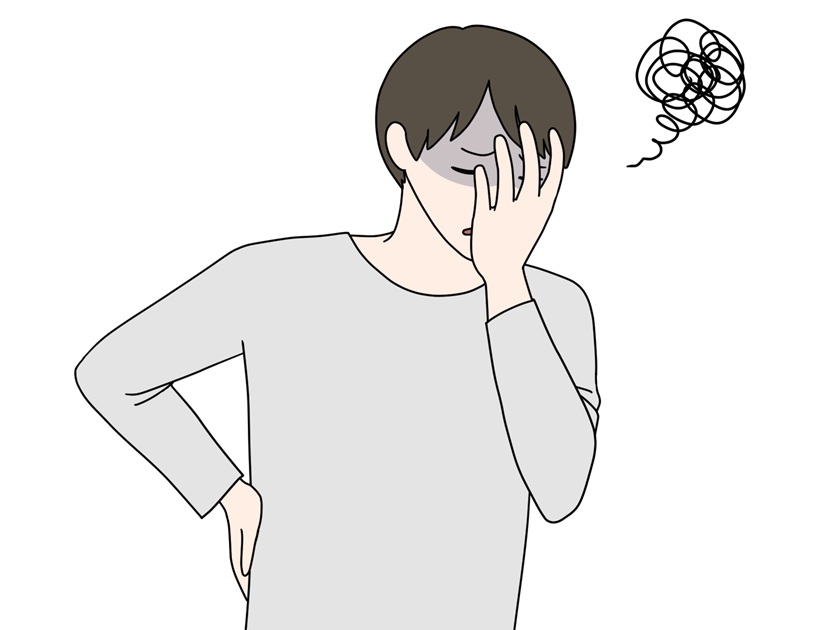
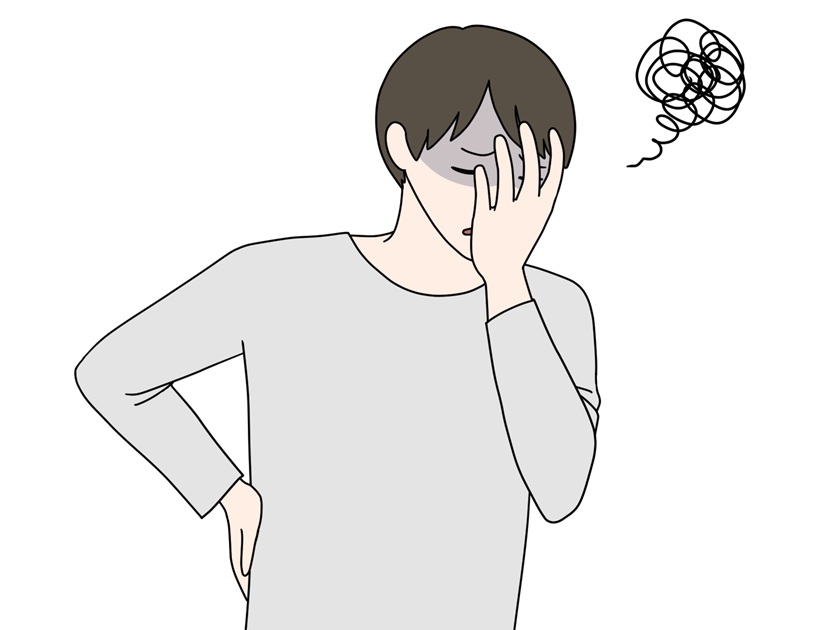
私は過去に一度、ケアマネや介護事務所へ相談したことがあります。一度は改善されるものの、しばらくするとまた同じことが繰り返される結果に。



やっぱり続かないんだ…😢
そう思うと、相談する気力すら失われ、「また言っても同じだろう」と諦めてしまう自分がいます。
人手不足の現実と感謝の気持ち


ただ一方で、私はヘルパーさんへの感謝の気持ちも強く持っています。
私の生活はヘルパーさんなしには成り立ちません。普段の介護や粗相時の予洗いなど本当にありがたく感謝しています。
今はどの産業でも人手不足ですが、介護現場は特に深刻です。厚生労働省の資料によると、介護事業所の約8割が人手不足を感じている統計もあります。
参考:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)資料1(令和5年7月24日)
そんな中で母を支えてくれる存在に、本当に感謝の思いで一杯です。だからこそ、私はヘルパーさんに意見しないようにしています。
もし無理に注文を重ねて、ヘルパーさんにストレスがかかり、母への態度が悪化したり、最悪の場合に介護拒否、暴力や窃盗につながるのでは…という不安もあるからです。
昨今のそんな事件報道の多さも要因の一つです。



ありがたいけれど、違和感もある😥



不満はあるけれど、言えない😫
この葛藤こそ、我々介護者の現実だと思います。
諦めて選んだ私の工夫


帰宅後すぐに元の配置に戻す時間を確保
最終的に私が選んだのは、「諦めて自分で工夫する」ことでした。たとえば整理整頓の問題については、帰宅後すぐに元の配置に戻す時間を作ることにしました。
ヘルパーさんに完璧を求めるのではなく、私の気持ちを守るために、自分の習慣に組み込むほうが早いと思ったからです。帰宅後すぐという動的フェーズに組み込むとすんなり行きます。
「完璧に解決」ではないが、自分の心を守るために割り切る
もちろん理想的な解決ではありません。でも、「ストレスをため続けるよりは、自分で直したほうが気持ちが楽になる」と思えるようになりました。
介護者自身が工夫して折り合いをつけるしかない現実もある。これが介護の難しさやストレスであり、理解されにくい部分かもしれません。
アンケートを利用する
年に1回ほどアンケートをお願いされることがあります。回収方法がヘルパー渡しだとすぐ読まれる可能性がありますが、介護事務所へ郵送の場合、ご意見・ご要望欄に思いの丈を書きましょう。
書く際は、我慢してきた期間を書くと改善に効果的だと思いますが、過度な期待は持たないほうが良いでしょう。
これは介護保険の範囲内かどうか分からず書こうか悩んでいる場合は、chatgptなどのAIに聞くのもオススメ!先述のコップの件は「お願いできる範囲内だと思います。」と言ってくれました。
私が割り切ろうと思ったきっかけ
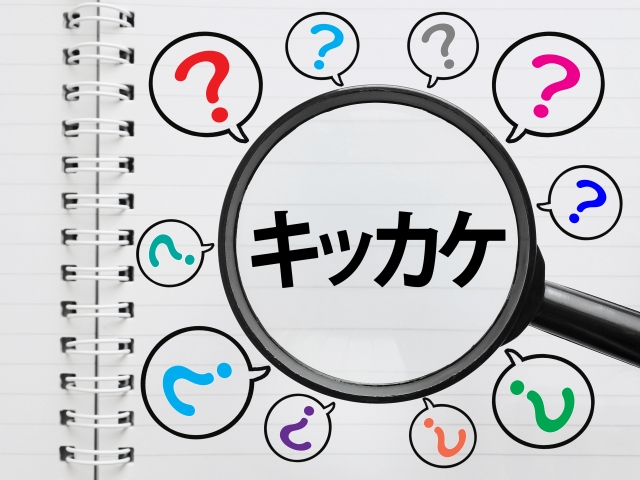
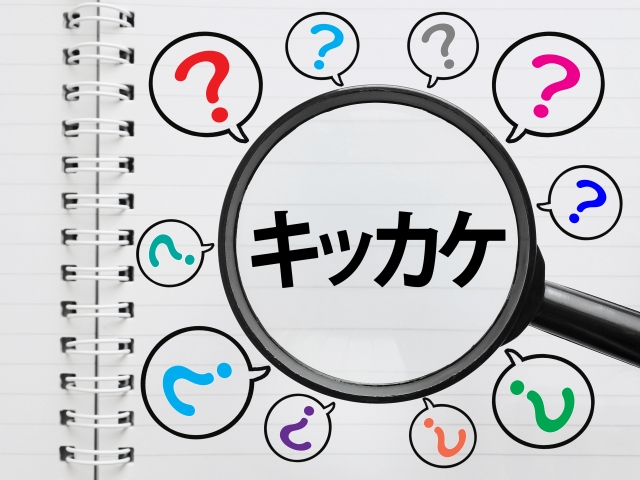
ある日帰宅すると、ヘルパーさんから一枚の付箋が、テーブルに残されていました。
ほうじ茶ティーバッグが無くなったのでストックから補充しました。
勝手にやってすいません。
ほんの短いメモでしたが、私はハッとしました。「補充してくれてありがたいのに、勝手にやることを謝られてしまった…。あちこちで色んな事を言われているんだろうか?…」と気づいたからです。
整理整頓を無視されることにストレスを感じていた私ですが、この書置きを見て、ヘルパーさんも悩みながら介護してくれているのだと知りました。
その瞬間、「完璧を求めても仕方ない。お互い人間だからズレはある。」と割り切る気持ちが少しずつ芽生えました。
以降、「違和感をゼロにする」のではなく、「多少のズレは工夫して受け止めよう!」という考えに切り替えたのです。
まとめ|介護者の心を守りつつ折り合う


ヘルパーさんに対して違和感を覚えるのは、決して珍しいことではありません。相談すれば一時的に改善するかもしれませんが、必ずしも理想通りにいくとは限らないのが現実です。
そんな中で大切なのは、介護者自身の心を守ることだと思います。我慢しすぎず、かといって全てをぶつけるのでもなく、時には「諦めて自分で工夫する」ことも選択肢の一つです。
自分のこだわりの強さを認めつつ、それを他人に求めても実現しない事もまた事実。そんな自分と折り合いをつける必要が出てくるのも介護の難しさの一つです。
感謝と不満、安心と違和感。その間で揺れ動くのが、介護者の本音です。同じように悩む方にとって、少しでも参考や共感につながれば嬉しいです。
在宅介護にまつわる人間関係あるあるを知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。大変な介護に追い打ちをかける人間関係の悩み。共感で癒さる方もいらっしゃると思い整理しました。
- ・悩み1|親
- ・悩み2|兄弟
- ・悩み3|ケアマネ
- ・悩み4|ヘルパー
防犯、お漏らし、食事など在宅介護の対策を知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。あると助かる便利グッズも多数紹介!
- ・対策1|防犯
- ・対策2|粗相
- ・対策3|粗相
- ・対策4|食事
- ・対策5|食事
- ・対策6|食事
- ・対策7|生活
-
自宅介護に必要なものは?介護者が助かる便利グッズ集(作成中!)
