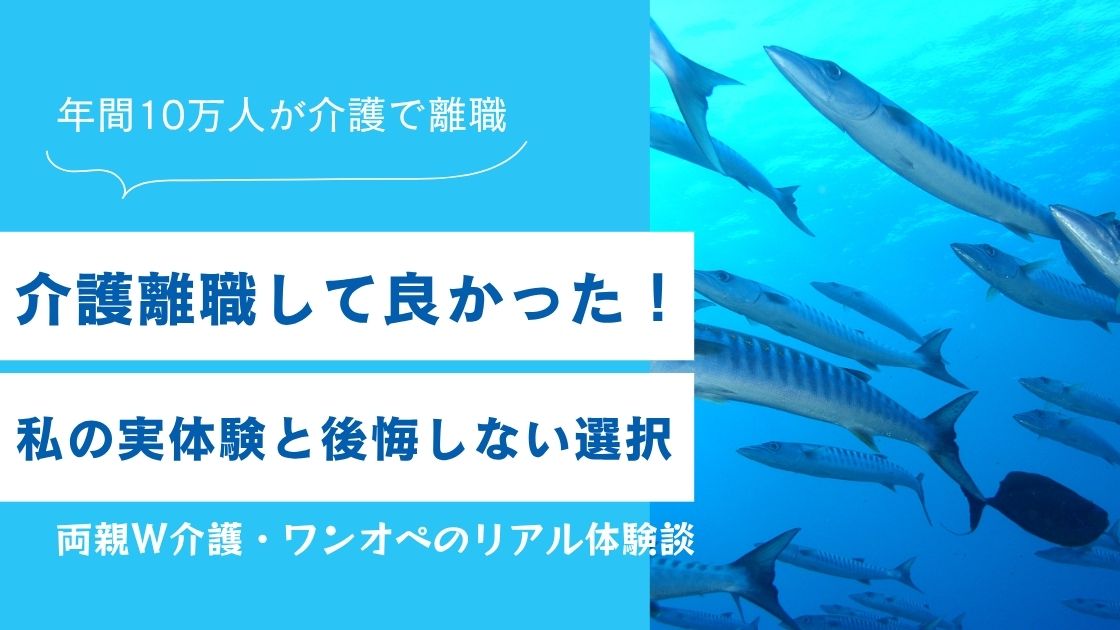アフィリエイト広告を利用しています。
 お台場
お台場こんにちは!お台場です。
今回は「介護離職した私の実体験」を解説します。
「介護離職」──検索すると「絶対するな」といった強い言葉や本に出会うこともあります。でも、それらは本当の意味で、介護者に寄り添っていないと感じます。
この記事では、私自身が介護離職をして「良かった」と心から思えた理由を、実体験と社会的背景を交えて正直にお伝えします。
- 介護と仕事の両立に限界を感じている方
- 介護離職を考えているが踏み切れず迷っている方
- 実際に介護離職した人の体験談を探している方
- リアルな体験談から「現実」を追体験できます
- 「良かった」と思えた理由が分かります
- 自分の判断材料の参考になります
私が介護離職を決断した理由
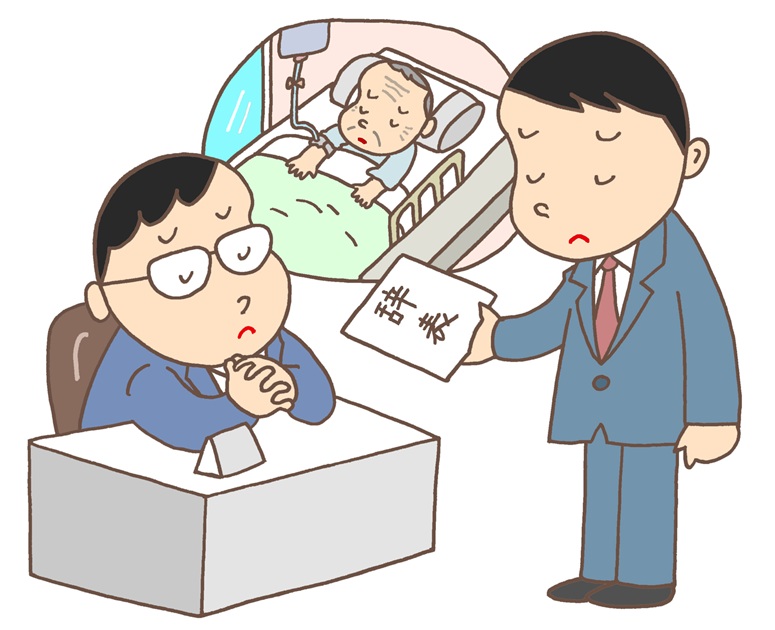
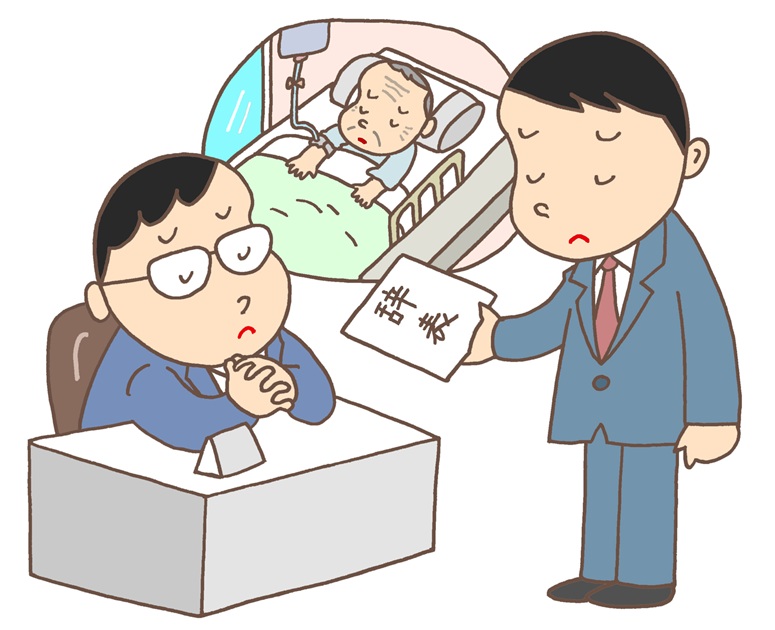
介護生活6年3ヶ月を経て、私は両立していた仕事を早期退職しました。その内、両親W介護は丸4年間です。
25年以上在籍した職場は居心地が良く、本当は少しでも長くそこで働きたい思いがありました。それでも退職を選ばざるを得なかったのは、いくつもの理由が重なり八方ふさがりになったからです。
職場への不満と怒り
休暇が足りない現実
両親W介護から父が亡くなった途端、介護休暇が年間10日から5日に半減。反対に、名義変更や相続登記など必要な手続きが増えたことで、介護休暇をすぐ使い切り、有給休暇も減少し、仕事との両立が困難な状況となった。
管理職を断ったのに押し付けてきた上層部への怒り
責任ある中間管理職を不本意に任される中で、介護休業を使える雰囲気はなく、実際には「制度があっても使えない」状態でした。
相続手続きで休んでいるのにケチをつけられた怒り
相続登記の義務化も重なり、手続きに追われ休暇を使わざるを得なかった。にも関わらず、後輩女性から嫌味を言われ、「もうこれ以上、嫌な人と関わりたくない」との思いに至った。
情けない同僚への呆れ
全てに余裕のない私の状況を知ってか知らずか、努力もせず頼ろうとする同期に、流石に嫌気がさした。
心身の限界と疲労
「もう限界以上働いた」と思えた心境
朝から晩まで介護と仕事に追われる毎日を約6年以上続け、「もう十分やった」と思えるほど疲れ切った。常に寝不足が付きまとった。
母の冬季うつが思いのほか酷く、心身が疲れ切った
母のうつ症状が重くなる冬は、真夜中に呼ばれることもあり、私自身も精神的に持ちこたえられなくなっていた。
退職後にやりたいことを見つけた
在職中に、早期退職後やりたいことが見つかった事も大きい。介護を続けながらも、仕事で身に着けたスキルや好きなことを生かして、新しい挑戦をしたいという思いが芽生えてた。
決断を後押しした私の状況とデータ
- 独身で身軽、借金なし、生活できるだけの貯金があった。
- 退職当時、私は54歳、母は80歳。女性平均寿命の88歳で亡くなったと仮定すると、私は62歳。男性の健康寿命が72歳であり、たった10年しか猶予がないという事に愕然とした。
社会全体でも深刻化する「介護離職」


私の介護離職は特別なものではありません。厚生労働省の調査によれば、毎年およそ10万人が介護や看護を理由に離職しています。
離職者の多くは40代~50代という働き盛り世代で、本人や家族だけでなく、企業や社会にとっても大きな損失となっています。
「介護離職ゼロ」を目指す国の施策
こうした事態を受けて、政府は「介護離職ゼロ」を掲げ、いくつかの制度を整えています。
- ・介護休業制度
-
要介護状態の家族1人につき、通算93日まで休業可能(分割取得も可)
- ・介護休暇制度
-
年間5日(2人以上なら10日)まで、1日または半日単位で休暇取得が可能
- ・両立支援助成金
-
企業が仕事と介護の両立に取り組んだ場合に支給
- ・地域包括支援
センター強化 -
地域で介護に関する相談を受けられる窓口を整備
国も対策を進めてはいますが、現実には「介護離職ゼロ」の実現にはほど遠いのが現状です。
介護離職が減らない理由(私の実感)


私自身が体験して痛感したのは、制度があっても現場では機能しないということでした。
介護休業は実際に取れなかった
私の職場は約20人と小規模で、介護と仕事を長期間両立していたのは私が初めて。そんな組織状況もあって管理職を押し付けられ、「介護休業を取れる雰囲気」自体がありませんでした。
職場の理解は最初だけ
介護を始めた当初は理解してくれる人もいましたが、長期間介護を続ける中で次第に薄れ、慣れへと変わりました。ある朝一番にこう言われたことがあります。
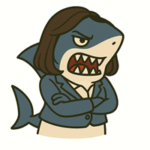
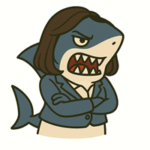
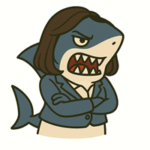
いい調子で介護休暇取ってますね~、日数考えて使ってますか❓



なんでそんな嫌味を言うんだろう…。本当に悲しい…😥
介護休暇5日はワンオペには足りない
完全に一人で介護を担う立場では、訪問サービス利用をしても5日間の介護休暇では到底足りません。最低でも要介護者1人につき10日は必要だと思います。
特に私の場合、2月末に父が亡くなった為、翌年度の介護休暇が5日に減少。そこに様々な名義変更や相続登記が重なり、役所や銀行に足を運ぶ機会が増えて介護休暇を早々に使い切り、有給休暇がどんどん減っていく状況に。
制度と現実のギャップ
国が制度を整えても、実際の職場環境や家族の事情によっては「使えない制度」になってしまいます。そのギャップこそが、10万人もの介護離職が今も毎年生まれている大きな原因だと感じています。
介護離職を考え中の方へ伝えたいこと
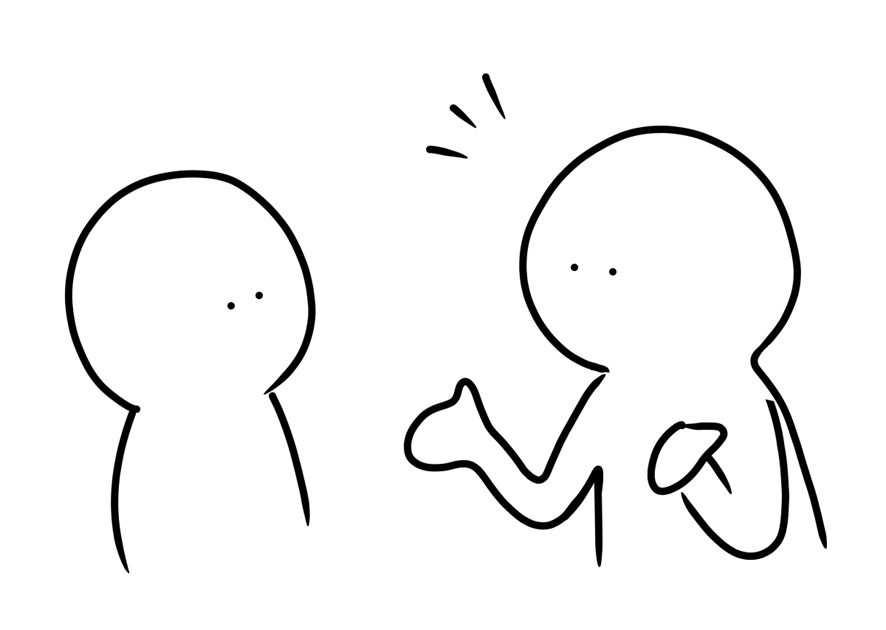
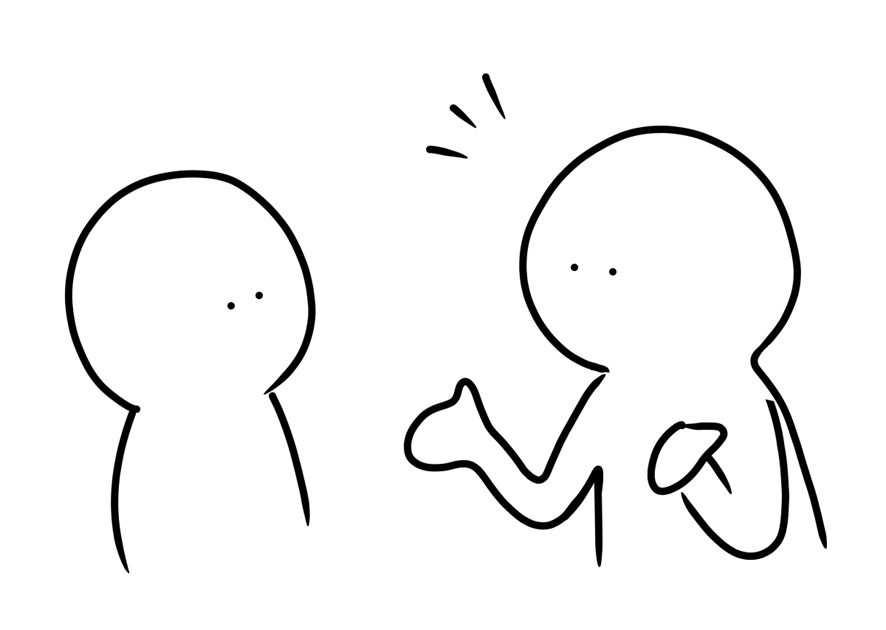
介護離職について検索すると、「絶対するな」といった強い言葉や、それをタイトルに掲げた本に出くわすことがあります。
しかし、私はそうした意見に正直、絶望していました。なぜなら、それらは本当の意味で介護者に寄り添っていないからです。
介護者のほとんどは心身の余裕がなく、疲れ切っています。「絶対するな」と言われると、介護と仕事の両立を無理してでも頑張れと更に追い詰められる気持ちになるからです。
離職前に考えておくべき準備
退職を決断する前に、まずは生活の基盤を確認することが欠かせません。貯金の有無、借金や住宅ローンの有無、家族の協力体制など。
私の場合は「独身で借金なし、ある程度の貯金あり」という条件は整っていましたが、収入が全く無くなる事への不安は大きかったです。
後悔しないために「自分軸」を持つ
制度や周囲の理解はあっても限界があります。最後に残るのは「自分が納得できるかどうか」。
「絶対するな」と外から言われても、それは他人の物差しです。大切なのは、自分の人生をどう納得できる形で選ぶかだと思います。
無理を続けるよりも、選択する勇気を
介護は長期戦です。無理を続ければ、体も心も壊れてしまいます。「絶対するな」という声に縛られて苦しむよりも、自分の状況に合った選択をする勇気を持つことの方が大切です。
再就職の可能性も視野に入れて
まずは心身の疲れをしっかり休ませることが最優先です。疲れが取れたら再就職を考えても良いでしょう。
以前は「50代での再就職は難しい」と言われていましたが、今は人手不足が深刻化しています。条件を高望みしなければ、家の近くでも働けるチャンスはあります。
「辞めたら終わり」ではなく、「一度区切ってまた働く道もある」と考えられるだけで、心がずっと軽くなります。
介護離職〇年目の今、感じていること


毎年、正直な気持ちを順次更新していきます。
【1年目】令和6年度
- 退職直後は引継ぎ疲れで燃え尽き症候群に。治るのに2週間ほど掛かりました。管理職の大変さや一部同僚からの嫌味に苦しむ日々から解放され、ホッとしています。
- 早期退職後、人と話す機会が圧倒的に少なくなり、人恋しく辛かったです。しかし私は元々、集団よりも単独行動が好きなので、これも2週間ほどで慣れました。
- 年金手続きやブログ準備で新鮮な日々。スケジュールを整えるのに時間がかかったが、離職して良かった。全く後悔はない。
- 「時間が足りない」と焦る毎日から解放され、母の冬季うつにも落ち着いて向き合えた。
【2年目】令和7年度
- 生活ペースが安定し、ブログ作成も軌道に乗って楽しい日々。
- 収入はまだゼロで不安もあるが、目標設定で心を保っている。
- それでもやはり、介護離職を選んで本当に良かった。全く後悔はない。
まとめ


私にとって介護離職は、間違いなく「良かった」選択でした。職場での怒りや不満から解放され、母の介護にしっかり向き合えるようになり、自分の新しい挑戦も始められたからです。
ただし、介護離職は誰にとっても簡単な選択ではありません。経済的な準備や家族の状況、再就職の見通しなど、考えるべきことはたくさんあります。
そして何よりも大切なのは離職した後、まず自分の心身をしっかり休ませることです。介護は待ってくれませんが、自分の体制を整えることが介護を続ける力につながります。
世間では「介護離職は絶対するな」という言葉や本もあります。他人の声に流されるのではなく、自分自身が納得できるかどうかを大切にしてほしいです。
介護離職はゴールではなく、新しいスタート。あなたにとっての最適な答えを探しながら、少しでも心穏やかに介護と向き合っていけることを願っています。
防犯、お漏らし、食事など在宅介護の対策を知りたい方は、こちらの連載記事がおすすめです。あると助かる便利グッズも多数紹介!
- ・対策1|防犯
- ・対策2|粗相
- ・対策3|粗相
- ・対策4|食事
- ・対策5|食事
- ・対策6|食事
- ・対策7|生活
-
自宅介護に必要なものは?介護者が助かる便利グッズ集(作成中!)