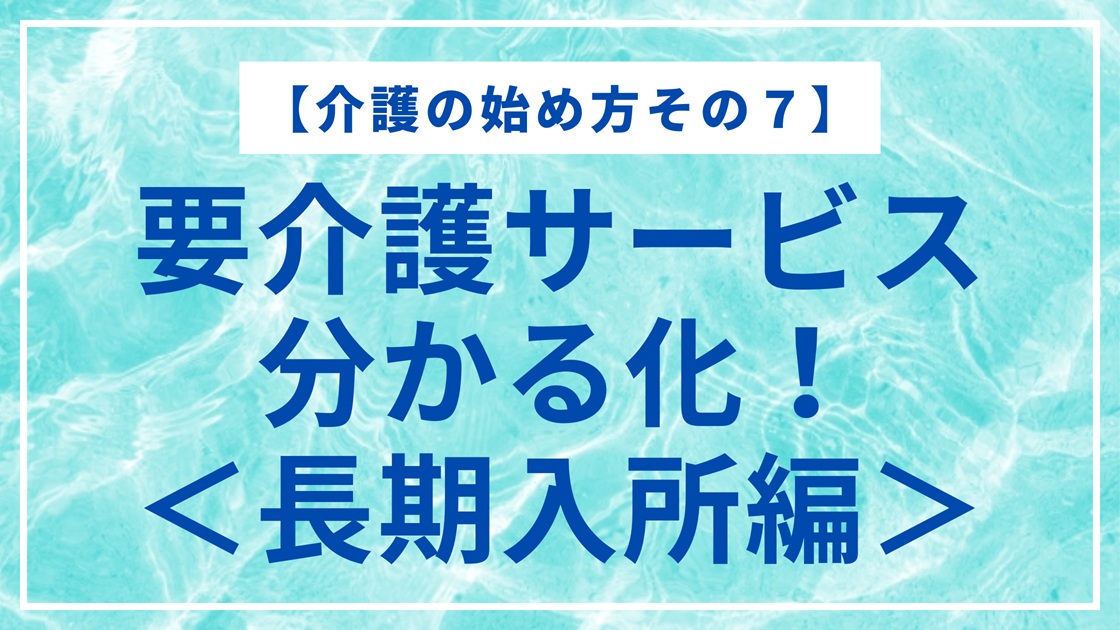※アフィリエイト広告を利用しています。
 お台場
お台場こんにちは!お台場です。
今回は「要介護サービス<長期入所編>」を解説します。
介護をしていると、こう感じることがあります。
「このまま在宅介護を続けるのは無理かもしれない…」
特に要介護3以上になると、夜間の見守りや排泄介助などが必要になり、在宅介護では支えきれないケースも。
そんなときに選択肢として挙がるのが、「老人ホーム等への長期入所」です。
この記事では、約64万人(*1)と最も利用者の多い特養(特別養護老人ホーム)を中心に、長期入所できる施設の種類や費用、申し込みの流れなどをわかりやすく解説します。
*1. 厚生労働省R3実績(下表参照)
- 老人ホームってどんな種類があるの?と思っている方
- 費用や特徴も知りたいという方
- 親の痴呆が進行し、在宅介護に限界を感じている方
- 老人ホームの種類を詳しく理解できます。
- 費用や特徴を分かり易く解説!
- 探し方や手続き、申込方法が分かります。
長期入所(老人ホーム)は以下のように、公的5と民間3、混在1の計9施設あります。
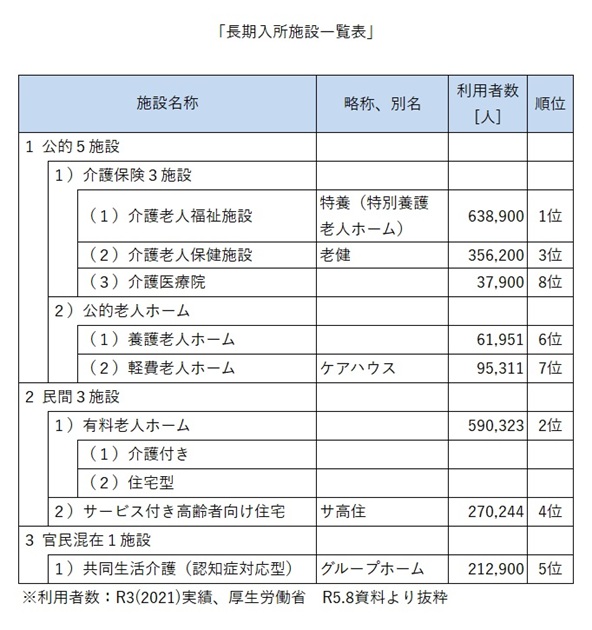
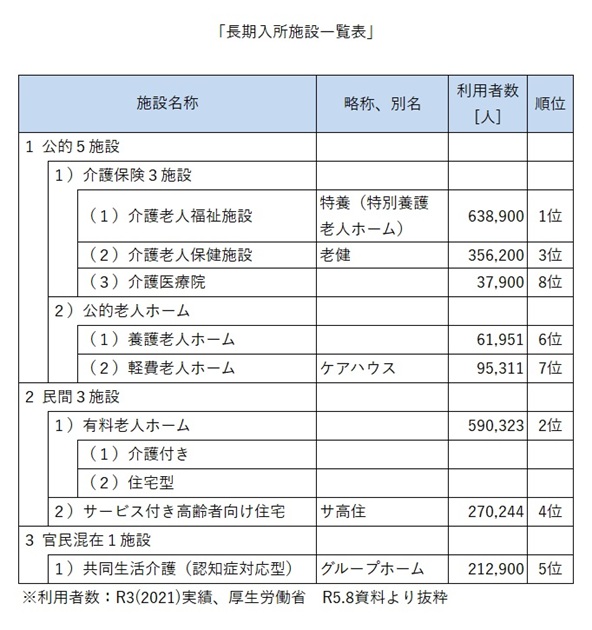
利用者数は1位が特養、2位が有料老人ホームとなっています。なんか似た名称が多くて分かりづらいですね。それでは、順番に公的施設から見ていきます。
公的5施設
公的施設は民間と比べると費用が安く済みます。対象者や費用、疾患等について表にしました。
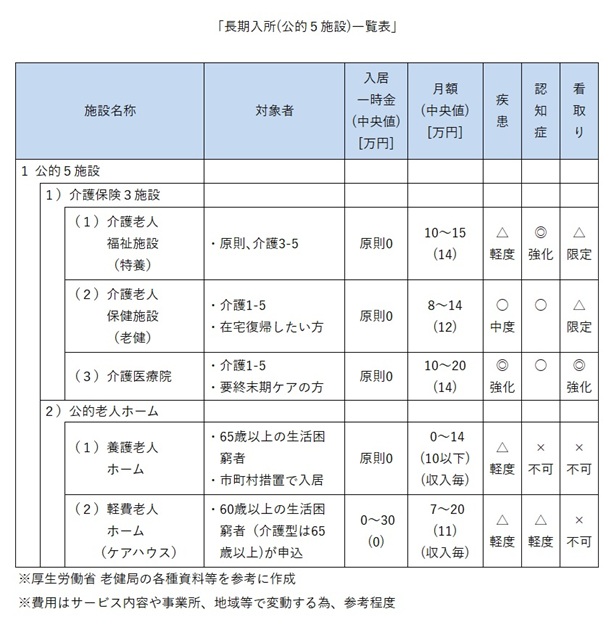
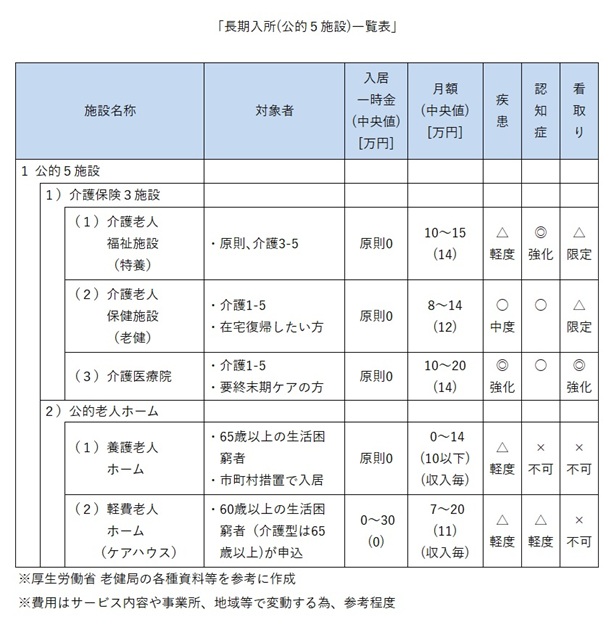
西暦2000年施行の介護保険法では、改正を経て介護保険3施設が新たに創設されました。月額は、参考までに費用の幅と中央値を載せています。
介護保険3施設


(1)介護老人福祉施設(特養)
介護老人福祉施設は「特養」(特別養護老人ホーム)とも呼ばれ、異なる名称ですが同じ施設を指しています。呼びやすい為、「特養」と呼ぶ場合がほとんどです。
名称が2つあるのは、根拠法が違う為です。介護老人福祉施設は「介護保険法」、特養は「老人福祉法」での施設名称。介護保険法第8条第27項で「介護老人福祉施設=特養」と定義され、要介護者の生活施設となっています。
施設数も多く、民間より安価な為、人気が集中していますが、入所期間が平均3.2年と長く、多くの方が順番待ちという現状があります。
a.対象者
- 原則、要介護3~5
- 軽疾患や認知症の方
- 定員30人未満の施設は在住者限定
b.費用
- 入居一時金:原則0円
- 月額:10~15万円(中央値14万円)
c.内容
- 生活支援、機能訓練
- 療養上の世話
- 在宅復帰が目標
- 看取りは施設で差があり、外部医療機関との連携が主流
d.特徴
- 生活介護中心で医療は最低限
- 認知症の方が多い
- 施設多数(全国約10,000ヶ所)あるが入所期間が平均約3.2年と長く、待機者多い。
- 要介護3~5の待機者25.3万人(厚生労働省2022年調査)→25人/施設の待機者という計算



生活支援や機能訓練ってどんなことするの?😥



「生活支援」はヘルパーさんが食事や入浴等を支援、「機能訓練」は専門指導員が歩行訓練やレク等で機能を維持していくよ~😊



「特養」って在宅復帰が目標なの?😥



そうなんだよね~。けど退所理由の最多は死亡69%、次いで入院24%。家庭復帰は僅か2%なんだよ~😅
(厚生労働省令和元年調査)
続いて、「老健」を見ていきます。
(2)介護老人保健施設(老健)
介護保険法を作った際、老人福祉法の「老人保健施設」を介護保険法へ移行し「介護老人保健施設」とした経緯があり、よく「老健」と略して呼ばれます。
要介護者の在宅復帰が目標で、平均10ヶ月で自宅に戻る方が多い。
a.対象者
- 要介護1~5
- 在宅復帰したい方
b.費用
- 入居一時金:原則0円
- 月額:8~14万円(中央値12万円)
c.内容
医師や看護師管理下で以下を実施
- 生活支援、機能訓練、リハビリ
- 介護や医療
- 在宅復帰が目標
d.特徴
- リハビリ重視
- 施設多数(全国約4,000ヶ所)あり、入所期間が平均10ヶ月と短い。
- 退所理由の最多は家庭36%、次いで入院33%
次は介護医療院を説明していきます。
(3)介護医療院
介護療養型医療施設を廃止(2024年3月末)し、代替の「介護医療院」を新設。要介護者の長期療養及び生活施設となっています。施設数は少ないが、介護療養型医療施設の廃止に伴い、年々微増している。
長期療養や終末期ケアが必要な方が主な対象で、入所期間は非常に短く平均6ヶ月となっています。
a.対象者
- 要介護1~5
- 長期療養が必要な方
- 看取りを含め、終末期ケアが必要な方
b.費用
- 入居一時金:原則0円
- 月額:10~20万円(中央値14万円)
c.内容
- 医師常駐&看護師24時間配置
- 機能訓練、療養上の管理
- 看護、介護
d.特徴
- 医療と介護の両立
- 長期療養と終末期ケア対応
- 施設少数(全国約600ヶ所)、入所期間は非常に短く平均6ヶ月
- 退所理由の最多は死亡52%、次点で入院20%
続いて、公的な老人ホームについてです。
公的老人ホーム


養護老人ホームと軽費老人ホームの2種類ありますが、共に生活困窮者の為の老人ホームです。要介護認定は必要なく、老人福祉法管轄の施設。
養護老人ホームは市町村からの措置で入居、軽費老人ホームは自身の申込で入居といった違いがあります。外部の介護サービス利用も可能で、要件を満たし、介護保険法の特定施設となっている施設もあります。
(1)養護老人ホーム
a.対象者
- 65歳以上の生活困窮者が市町村措置で入居
- 自立、軽疾患
b.費用
- 入居一時金:原則0円
- 月額:0~14万円(中央値10万円以下:収入毎)
c.内容
- 医療体制無し、介護サービス無し
d.特徴
- 外部介護サービス利用可
- 少数(約900ヶ所)※特定施設約400ヶ所含む
(2)軽費老人ホーム(ケアハウス)
a.対象者
- 60歳以上の生活困窮者(介護型のみ65歳以上)が申込
- 自立、軽疾患
- 要介護認定なくても入居可
b.費用
- 入居一時金:0~30万円(中央値0)
- 月額:7~20万円(中央値11万円:収入毎)
c.内容
- 介護対応の介護型ケアハウス等4種ほどある。
d.特徴
- 外部介護サービス利用可
- 少数(約2,000ヶ所)※特定施設約500ヶ所含む
続いて、民間3施設について見ていきましょう。
民間3施設
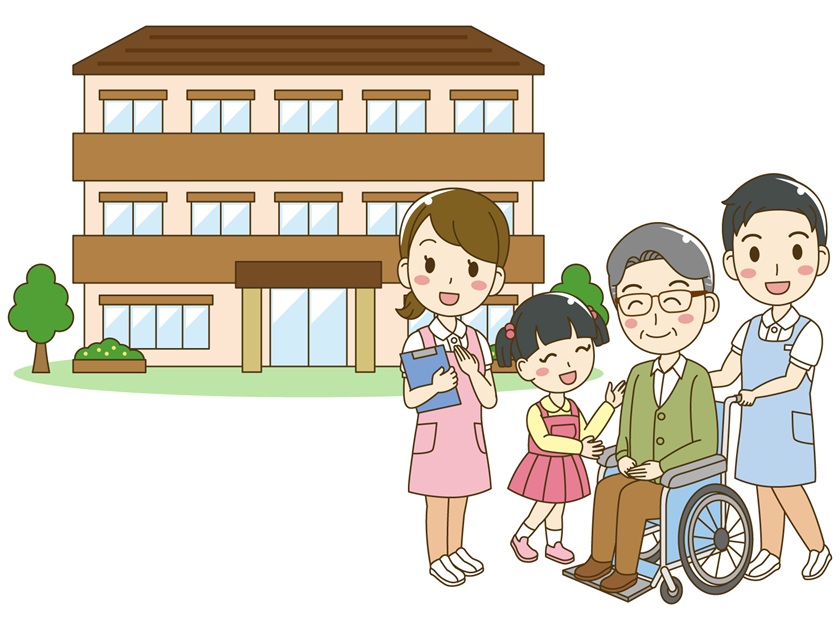
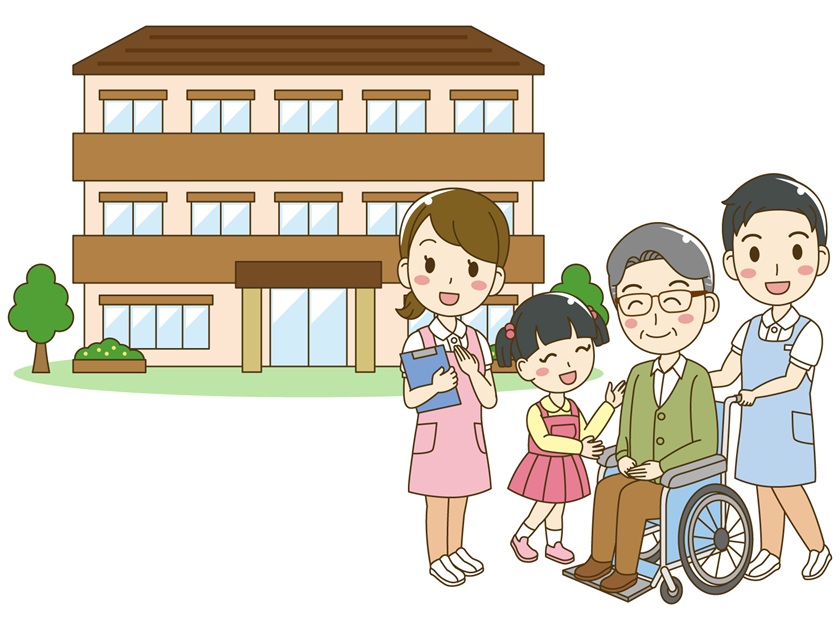
民間施設は公的施設と比べると、費用が割高です。対象者や費用、疾患等について表にしました。
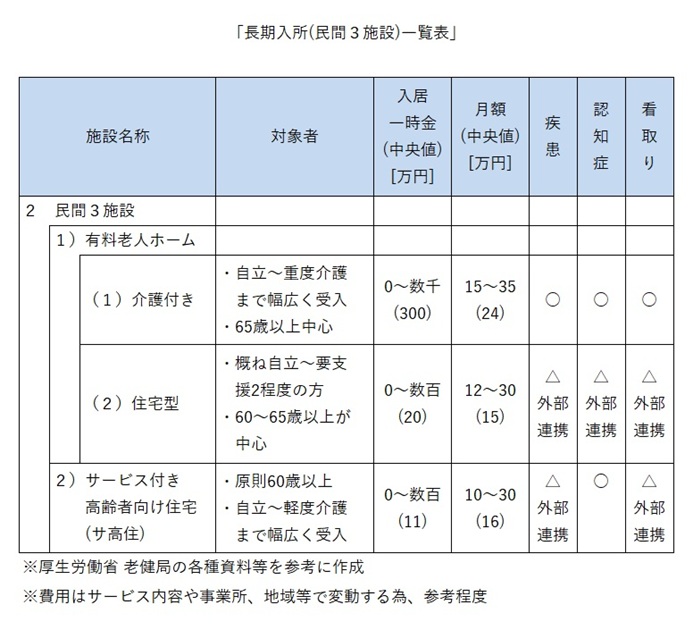
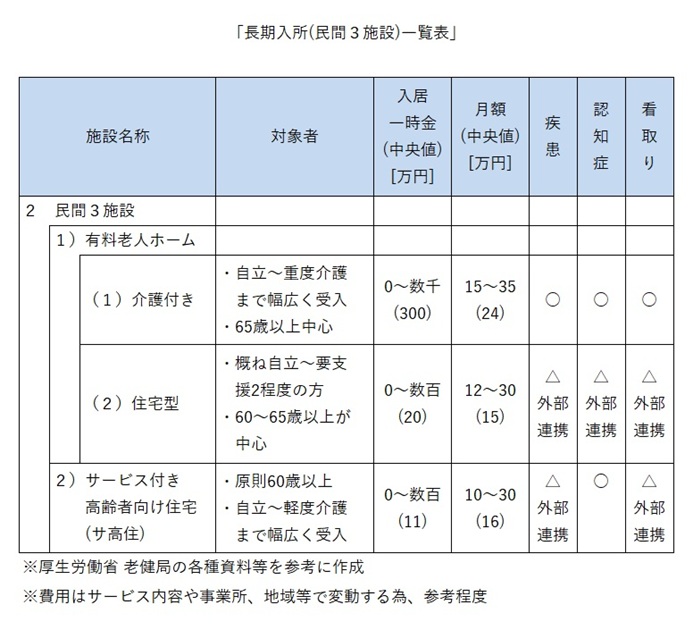
有料老人ホーム
(1)介護付き
介護保険法の特定施設。都道府県等の指定を受けた有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」といいます。介護保険サービスをホームが直接提供、一元管理できる利点があります。
a.対象者
- 自立~重度介護まで幅広く受入
- 65歳以上中心
b.費用
- 入居一時金:0~数千万円(中央値300万円)
- 月額:15~35万円(中央値24万円)
c.内容
- 生活支援、身体介護、リハビリ、レクリエーション
- 健康管理(看護師24h常駐)、緊急時対応
d.特徴
- 重度疾患や看取りまで一貫対応可能(月額に含む)
- 介護保険サービスをホームが直接提供
- 入居一時金0~数千万円と施設差大、1億円超もあり(東京)
- 多数(約4,000棟)
(2)住宅型
介護が付かない有料老人ホームを「住宅型有料老人ホーム」といい、老人福祉法管轄の施設となります。
a.対象者
- 概ね自立~要支援2程度の方
- 60~65歳以上が中心
b.費用
- 入居一時金:0~数百万円(中央値20万円)
- 月額:12~30万円(中央値15万円)
c.内容
- 生活支援(清掃、安否確認)
- 食費は3食で月額約4~9万円(別料金)、外食も可能
d.特徴
- 医療、認知症ケア、看護、介護等は外部サービス頼み、別料金
- 入居一時金0~数百万円と施設差大、1億円超もあり(東京)
- 多数(約10,000棟)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
2011年(平成23年)、高齢者住まい法で創設された新しい住宅制度。バリアフリーや見守りサービスを備え、住み慣れた地域で自立し安心して暮らせる、「住まいとサービス」を一体提供する住宅。
a.対象者
- 原則60歳以上
- 自立~軽度介護まで幅広く受入
b.費用
- 入居一時金:0~数百万円(中央値11万円)
- 月額:10~30万円(中央値16万円)
c.内容
- 安否確認、生活相談
- 食事、生活支援(オプション)
- 外部介護、医療サービス(オプション)
d.特徴
- バリアフリー設計、緊急通報装置付き
- 一般型(自立〜軽度介護)と介護型(要介護者向け)がある。
- 多数(約8,000棟)※特定施設約700棟含む。
続いて、官民混在しているグループホームについて、見ていきます。
官民混在1施設
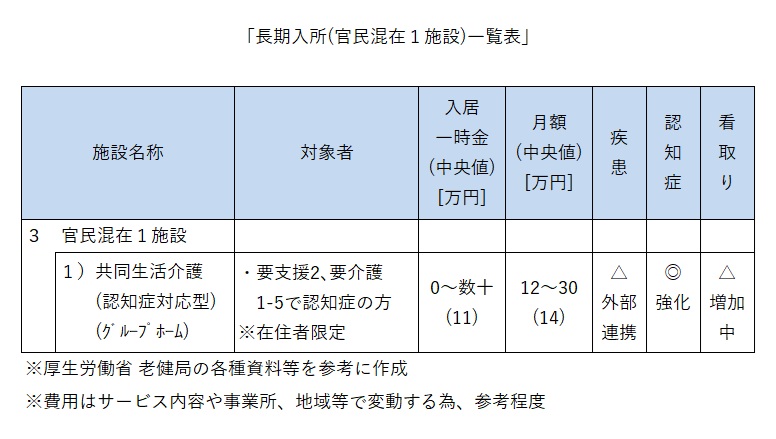
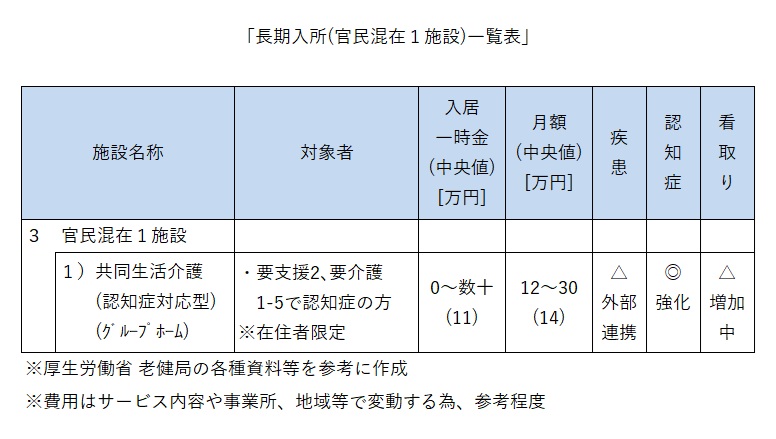
共同生活介護(認知症対応型)|グループホーム


2000年の介護保険法施行と共に制度化され、2006年に地域密着型サービスとなり、在住者限定のサービスになっています。少人数制で家庭的という特徴もあります。
a.対象者
- 要支援2、要介護1-5で認知症の方
- 在住者限定
b.費用
- 入居一時金:0~数十万円(中央値11万円)
- 月額:12~30万円(中央値14万円)
c.内容
- 生活支援や介護、機能訓練等
- 24時間体制
d.特徴
- 5~9人の少人数制+介護スタッフが家庭的な雰囲気で共同生活する。
- 民家型やアパート型等多様な形態がある。
- 多数(約14,000)
- 設置主体は官民両方あり、営利法人が 最多54%
続いて、特養の利用に向けて、流れや手続きを解説します。
入所までの手続き|特養


入所希望の意思を伝え、候補施設の選定を依頼
実際に足を運んで雰囲気や職員の対応を確認。デイサービスやショートステイの併設サービスがあれば、短期間利用することで相性等を事前に確認できます。
介護認定情報、健康状態、生活歴などを記入
緊急度や介護度、家庭状況などで優先順位が決定
続いて、特養申込前のチェックポイントを整理しました。
チェックポイント|特養


- 家族が通いやすい立地か
- 看取りケアに対応しているか
- 医療処置がどこまで対応可能か(胃ろう、インスリン注射など)
- 居室のタイプ(個室・2人部屋・多床室)
- 施設の雰囲気やスタッフの印象
次は、よくある質問をカクちゃん、マンタ先生の会話で見てみましょう。
よくあるQ&A|特養


特養について、Q&Aで振り返ります。
Q. 特養の対象者について



特養は誰でも入れるの?😥



「要介護3以上」が原則だよ。けど家庭事情などで柔軟に対応されるケースもあるから、ケアマネさんに相談してみてね~😊
Q. 入所までの期間について



申し込みをして、すぐに入れる❓



都市部では数ヶ月〜1年以上待つこともあるよ‼️計算すると1施設当り25人も待機者がいるからね。特養への申し込みは複数個所できるから、多く申し込んでおくと良いよ~👍
5施設までなど制限ある市区町村もあるし、入所が決まったら他の申込を取り消すことも忘れないでね~😊
Q. 民間施設と特養の違い



民間施設はどう違うの❓



有料老人ホームなどの民間施設は費用が高めだけど、空きが多く、柔軟なサービスが魅力だよ~🌟
色んな疑問が整理されたところで、自宅付近にある特養を実際に探してみよう!
特養の探し方


厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」での探し方を説明します。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
上のリンクからアクセス↓




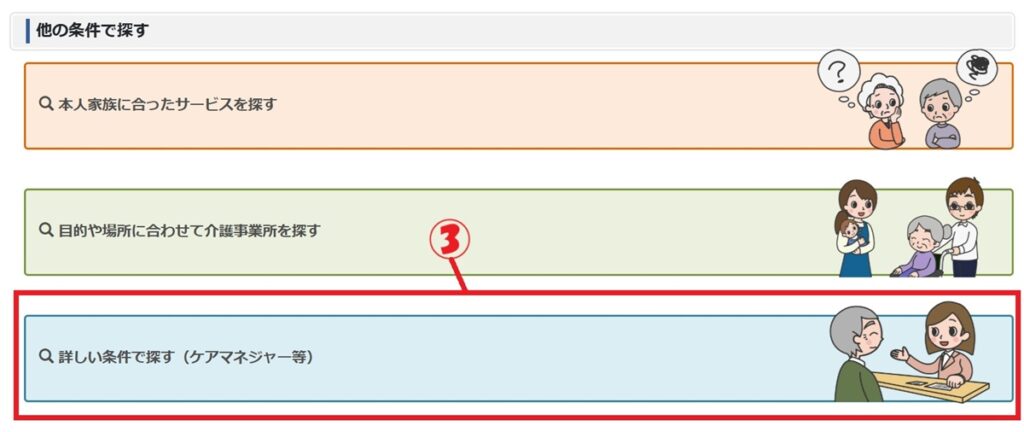
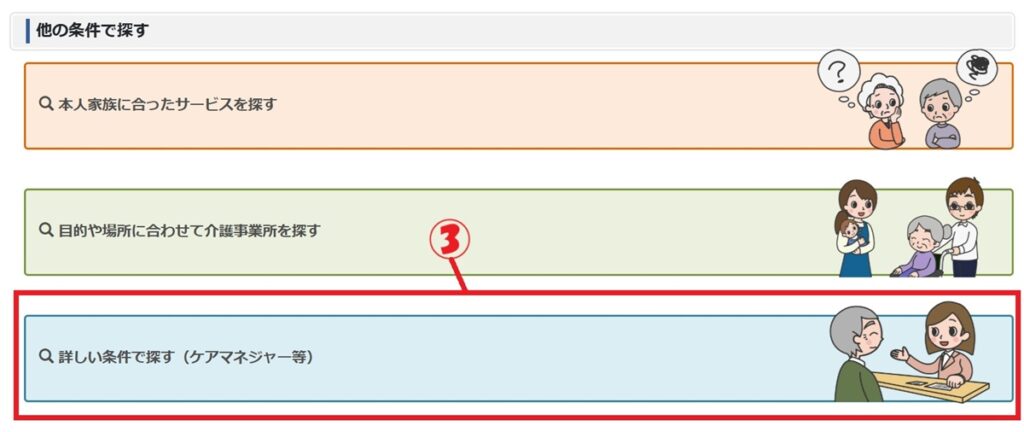
・サービスの種類:「介護老人福祉施設」
・事業所の所在地:「お住いの地区」
を選択し、一番下の「検索する」をクリック
※特養=介護老人福祉施設、他施設も複数選択可能
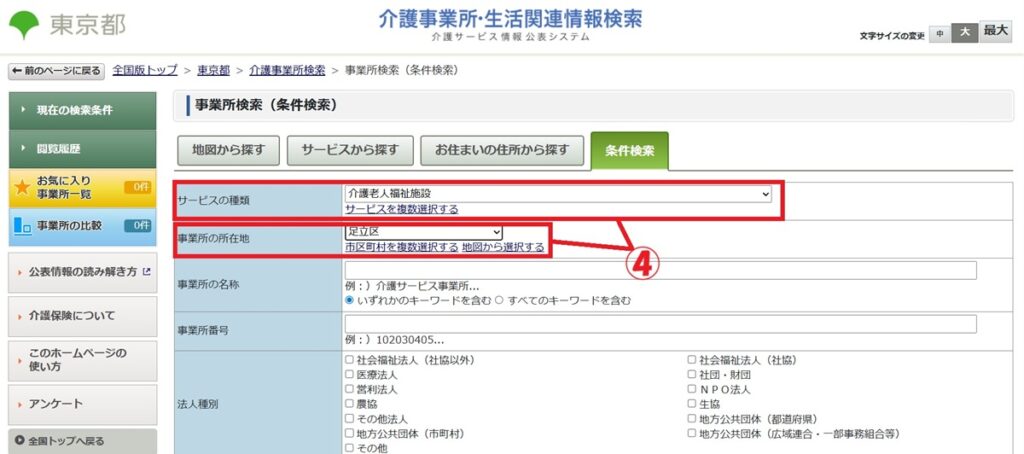
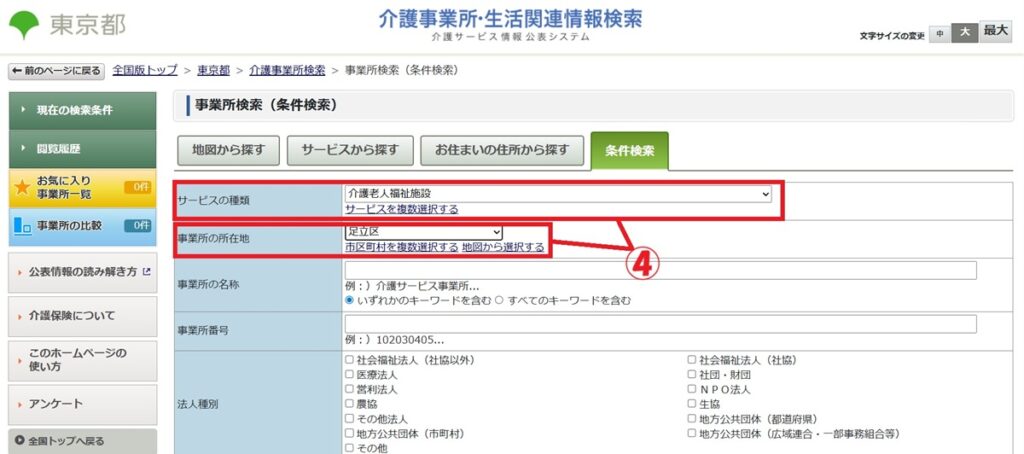
全件数表示できる件数に変更し、「地図を開く」をクリック
※件数変更しないと、地図上に表示されない施設があるので要注意!
※「空き人数」等で並び替え可能、空き人数情報は参考程度


右下にある◇マークをクリックすると、地図を拡大縮小&移動できるボタンが表示されます。自宅周辺で探す際に便利です。
気になる施設をクリックすると、施設情報が表示されます。「施設入所」の左の数字は、並び替えした条件での順位です。
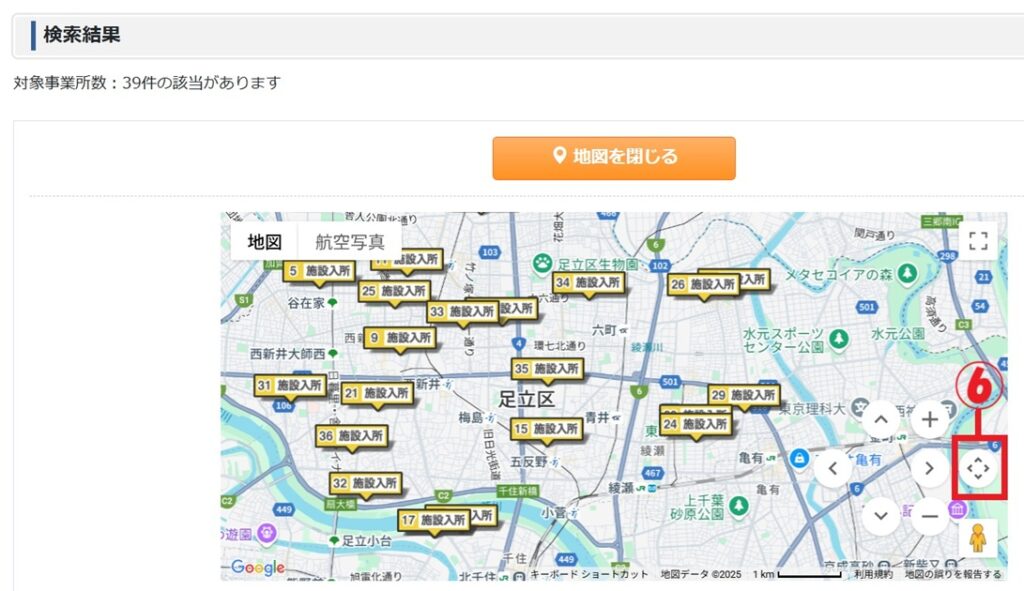
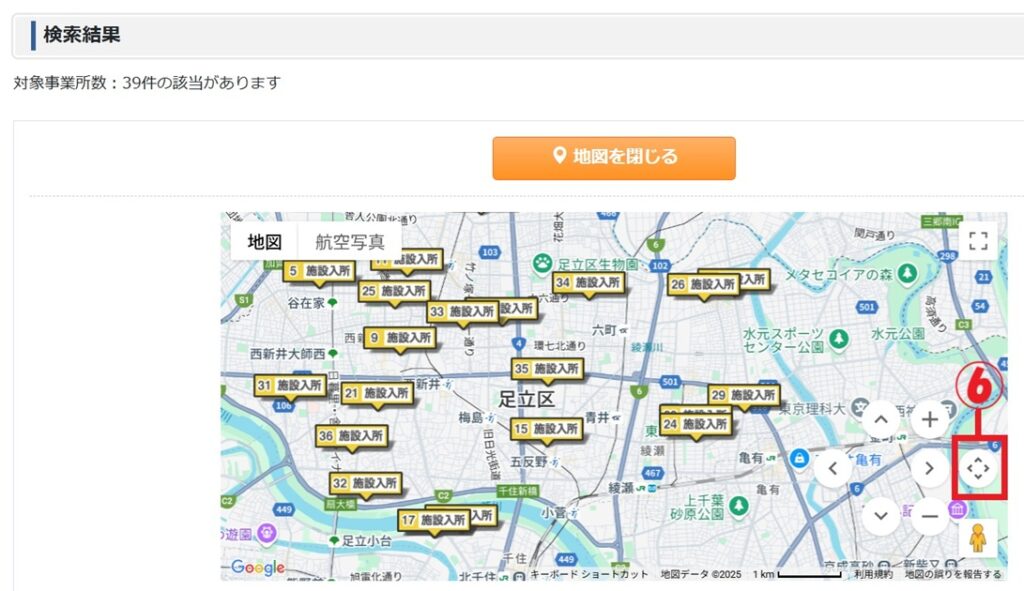
まとめ|後悔しない選択のために
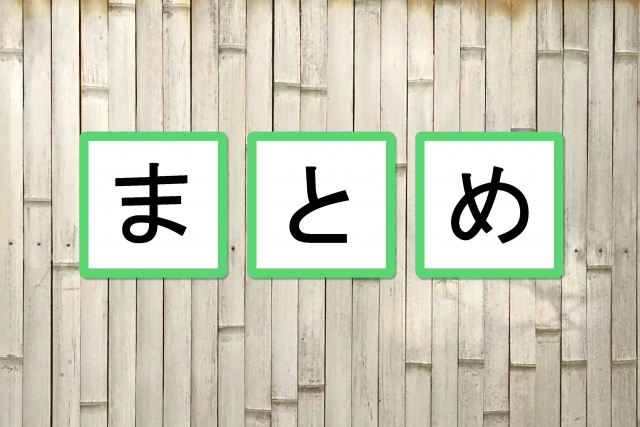
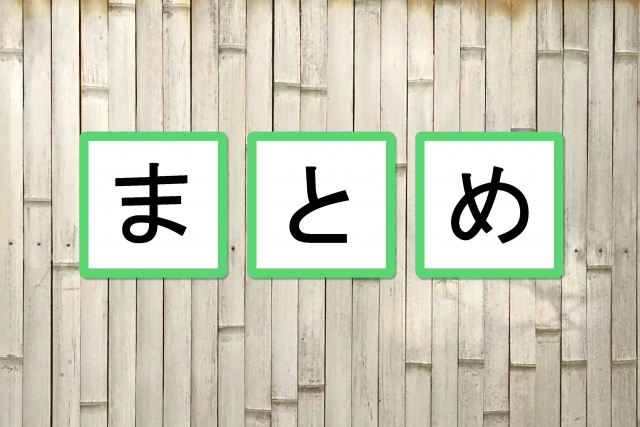
まとめとして、長期入所施設の詳細一覧表を作ったのでご参照ください。
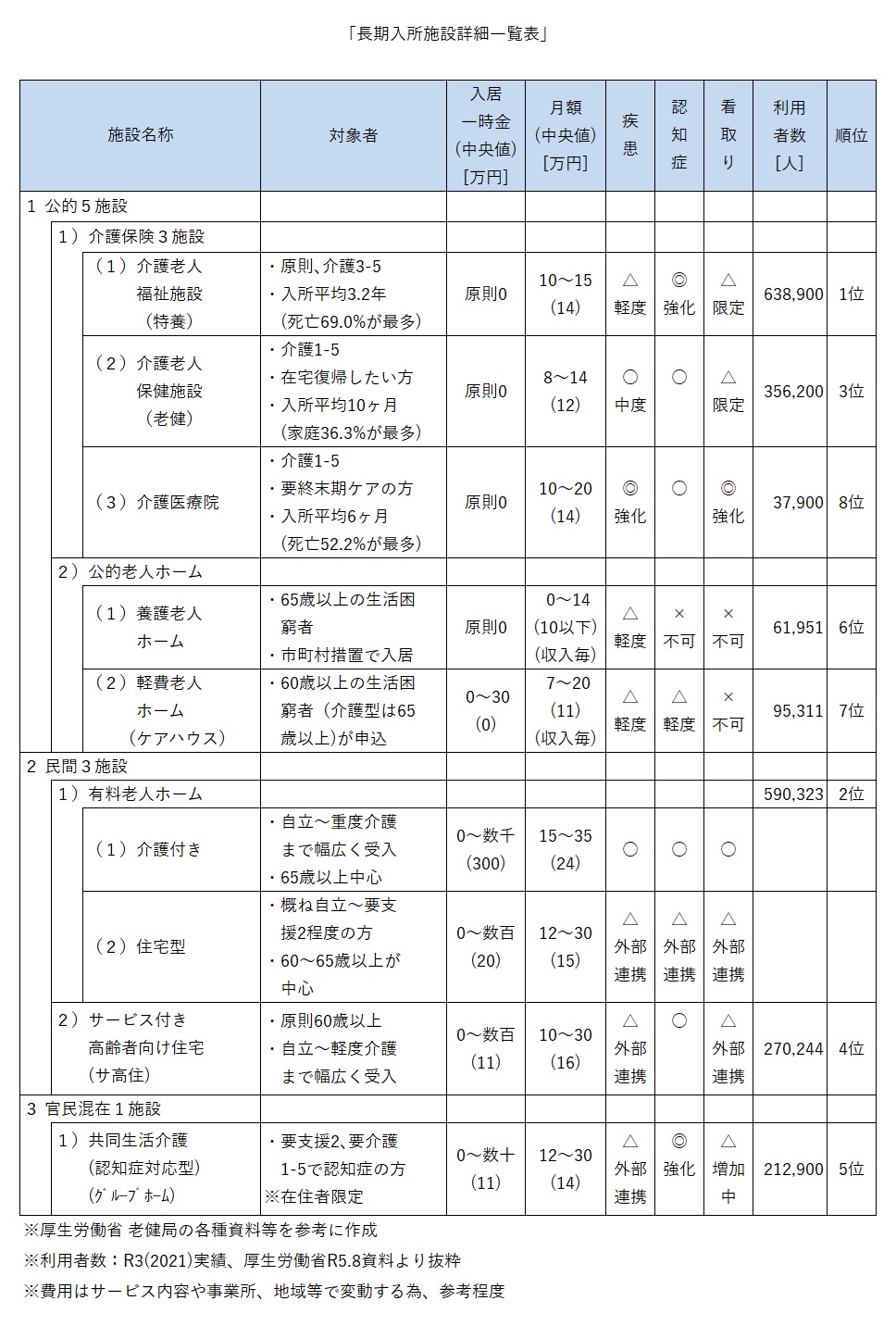
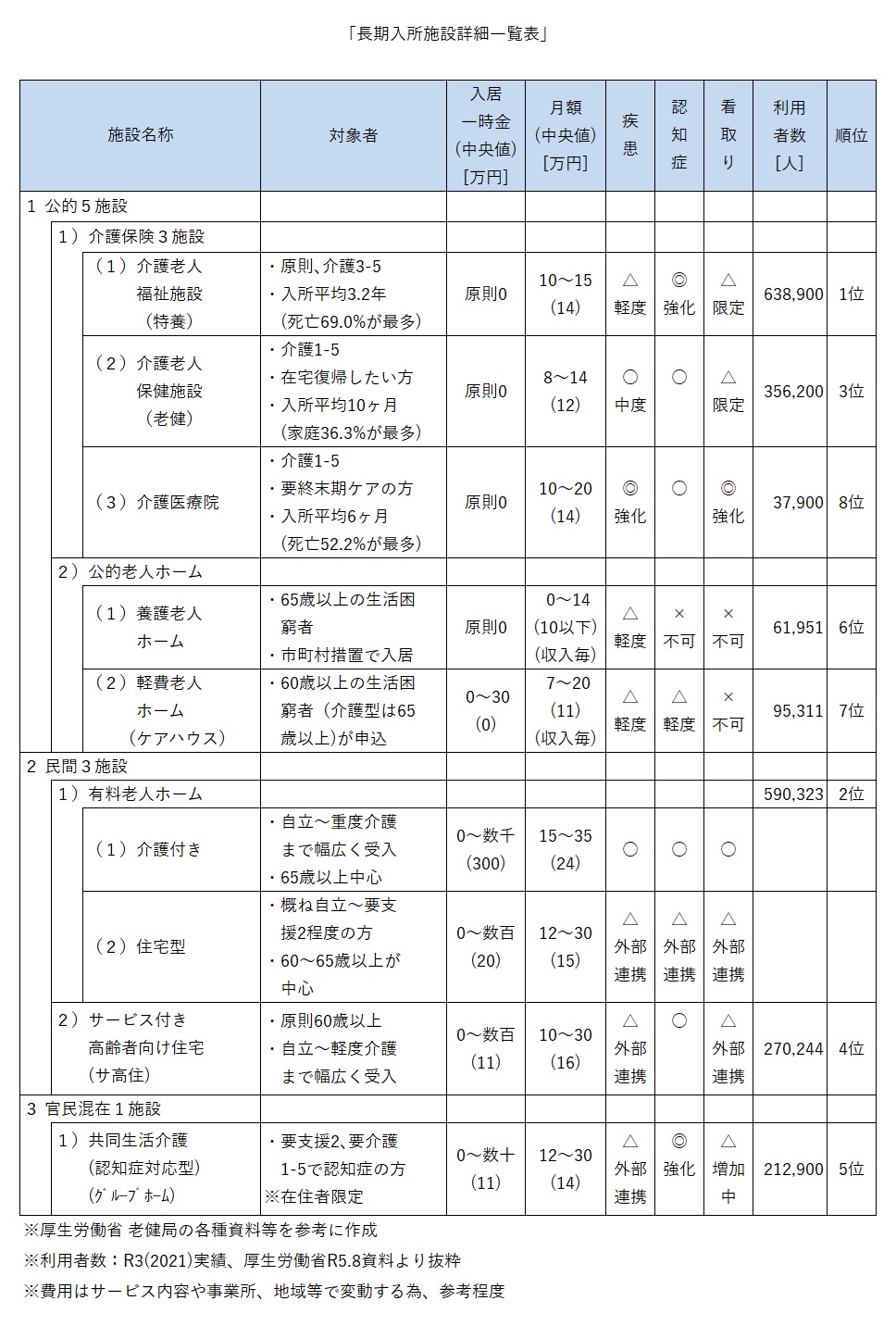
長期入所は、家族の介護負担を大きく軽減する重要な選択肢です。ですが、施設によって雰囲気やサービス、費用は大きく異なります。
見学・相談・比較をしっかり行い、「入ってよかった」と思える施設選びを目指しましょう。まずは、信頼できるケアマネージャーや地域包括支援センターに、少しずつ相談していきましょう。
連載記事【介護の始め方】もこれで終わりです。時間がない中、ここまでの読破、本当にお疲れさまでした。振り返り用に【介護の始め方1~7】へのリンクを貼っておきます。
これからも無理せず、自分自身を大切にしながら介護してくださいね。
在宅介護がこれからの方にはこちらの連載記事もおすすめです。ヘルパーさんなど第3者が自宅に入ることに、私は不安や抵抗感をすごく感じていました。私が実際に行った防犯対策や粗相対策、おすすめグッズをまとめまています。